神戸の桜はだいぶ満開に近付いていてきました。みなさんのお住まいや勤務先の近くの桜はいかがでしょうか?
特許の存続期間は原則として出願から20年ですが、医薬品の承認取得には開発から起算して概ね10年以上と非常に長い時間がかかります。そこで日本では、「医薬品特許に対して 」最長5年間の延長が認められています。
今日はこの延長制度の仕組みと注意点について解説します。
◆ 延長制度の基本:なぜ延長が認められるのか?
医薬品は、開発しても承認審査が終わるまで販売することができません。つまり特許を取得しても、国の承認を得なければ発明を実施して、権利者は市場から利益を得ることができないのです。そこで、法律の規制によって、”侵食された存続期間”を回復することを目的として制定された制度が特許延長制度なのです。
◆ 延長の対象となる行政処分とは?
医薬品に対しては具体的には以下のような処分に延長が認められます。
- 新薬の製造販売承認
- 用法・用量の変更に関する承認
- 新規適応症の承認
- 後発品に関わる製剤の一部変更承認(製剤特許対象)
◆ 延長の実態:特許1件に複数の延長?
実務上は、同じ特許に複数の延長がなされていることもあります。これは、異なる承認処分に基づく延長申請が認められているためです。
例えば:
- 同じ成分でもOD錠、カプセルでそれぞれ別の延長が存在
- 同一特許に対し、複数の製剤承認が紐づく
結果として、1件の特許に対して満了日が複数存在することもあり、注意が必要です。
◆ 特許が切れていても延長が効いている?
よくある誤解ですが、「特許が切れた=自由に使える」とは限りません。
1つの特許に対して延長登録のある部分とない部分が存在する場合があり、一部分だけが満了している場合は、延長登録が残っている部分については依然として独占が続いている場合があります。
そのため、商談や製剤開発においては、
「特許の延長登録が”どこに””いつまで”存在するか」をチェックすることが大切になってきます。
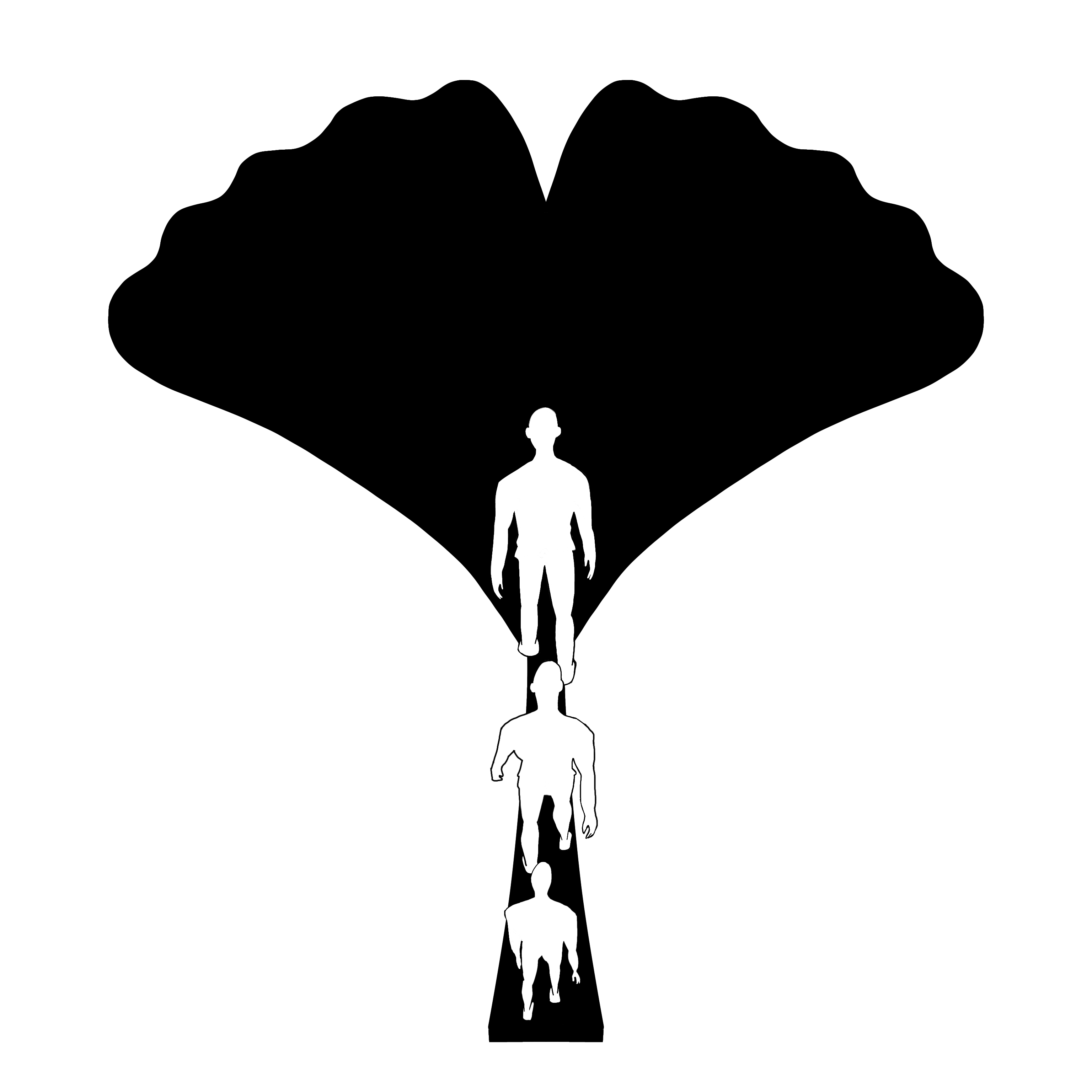
コメントを残す