製薬業界で特許という言葉を耳にする機会は多いですが、医薬品と関連する特許には「実際にどのような種類があり、それぞれが何を保護しているのか」この点について体系的に整理されている資料は意外と少ないものです。今回から3回に渡り、医薬品特許の基礎講座として、書いてきます。
本ブログでは、実務上押さえておきたい主要な医薬品特許の種類と、それぞれが果たす役割の違いについて解説します。
◆ 物質特許(成分特許):最も強力な“独占権”
有効成分(化合物)を保護する特許で、有効成分そのものはもちろん、有効成分を含む化合物群を保護しているものもあります。
創薬研究において、非臨床段階で有用な化合物が見出された際、まずは広い化合物群を出願し、その後実際に薬になりそうな有効性が高く毒性との乖離のある化合物を…、更に絞り込んで有効成分そのものを…、といったように何段階かに分けて出願するケースもあり、1つの品目に対して物質特許が1つであるとは限りません。
物質特許が残存している間は後発品の承認が降りることはないため、他者はその特許で保護された有効成分を含む製品を製造・販売できず、参入を排除する最も強力なバリアとなります。
◆ 用途特許:新たな治療対象や投与法への応用
有効成分(化合物)の疾患への適応や投与方法を保護する特許です。
日本では比較的通りやすく、ライフサイクル延長のために活用されることが多い特許です。また公知の物質であっても、新たな有用性が見出された場合には第二医薬用途*発明として特許出願されるケースもあります。
有効成分に対する効能効果が残存している場合は後発品の製造販売ができないため、物質特許と並んで強力なバリアとされています。
*例:シルデナフィル(狭心症→ED治療薬)、タダラフィル(前立腺肥大→AGA治療薬)
◆ 製剤特許:添加物や製剤技術に関する工夫
有効成分の安定性や溶出性を担保したり吸収性を良くするための製剤処方、いわゆるドラッグデリバリー(DDS)技術、コントロールドリリース技術、また製剤の服用のしやすさなどを高める技術を保護しています*。
特殊な製剤の場合、物質特許が切れたあとでも、製剤特許がジェネリックの参入を一定期間ブロックすることがあります。またジェネリック製販が先発と異なる製剤技術を用いて製剤を開発し、特許を取得している例もあります。
*例:OD錠、腸溶コーティング錠、徐放性カプセル、特殊な乳化製剤(リポソーム)など
◆ 製法特許:成分の合成ルートや精製技術を守る
原薬製造過程の工夫やコスト削減、高純度化を実現する技術を保護しています*。
原薬の合成ルートにおいて経由する中間体で、避けて通ることが困難な物質も強力な武器となります(いわゆる中間体特許)。ただし効率が悪くとも、別の合成ルートで原薬を製造することができれば、回避可能なため、ブロック力は物質特許ほど強くはありません。
*例:高収率での合成、重金属不純物の除去工程など
◆ 結晶形特許:優れた物性を示す化合物の形態
同じ有効成分でも、結晶の形(多形)*によって安定性や溶解性、製造時のハンドリングのしやすさなどに影響を及ぼす”物性”が異なる形態が存在します。この“形態”の違いに着目して出願されるのが結晶形特許です。
*例:有効成分(化合物)のI型、II型、無定形(アモルファス)、塩、溶媒和物など
実務上は物質特許切れ後の防御壁として活用されるケースも多く、先発・ジェネリック企業にとっては製品戦略の鍵となる
結晶形や製剤、製法といった周辺特許は、「本質的な権利」ではなくても、製品の商業化を阻む“実質的な障壁”として機能します。
つまり、開発候補となる医薬品は“何の特許で保護されているのか”を見極めることが非常に重要なのです。
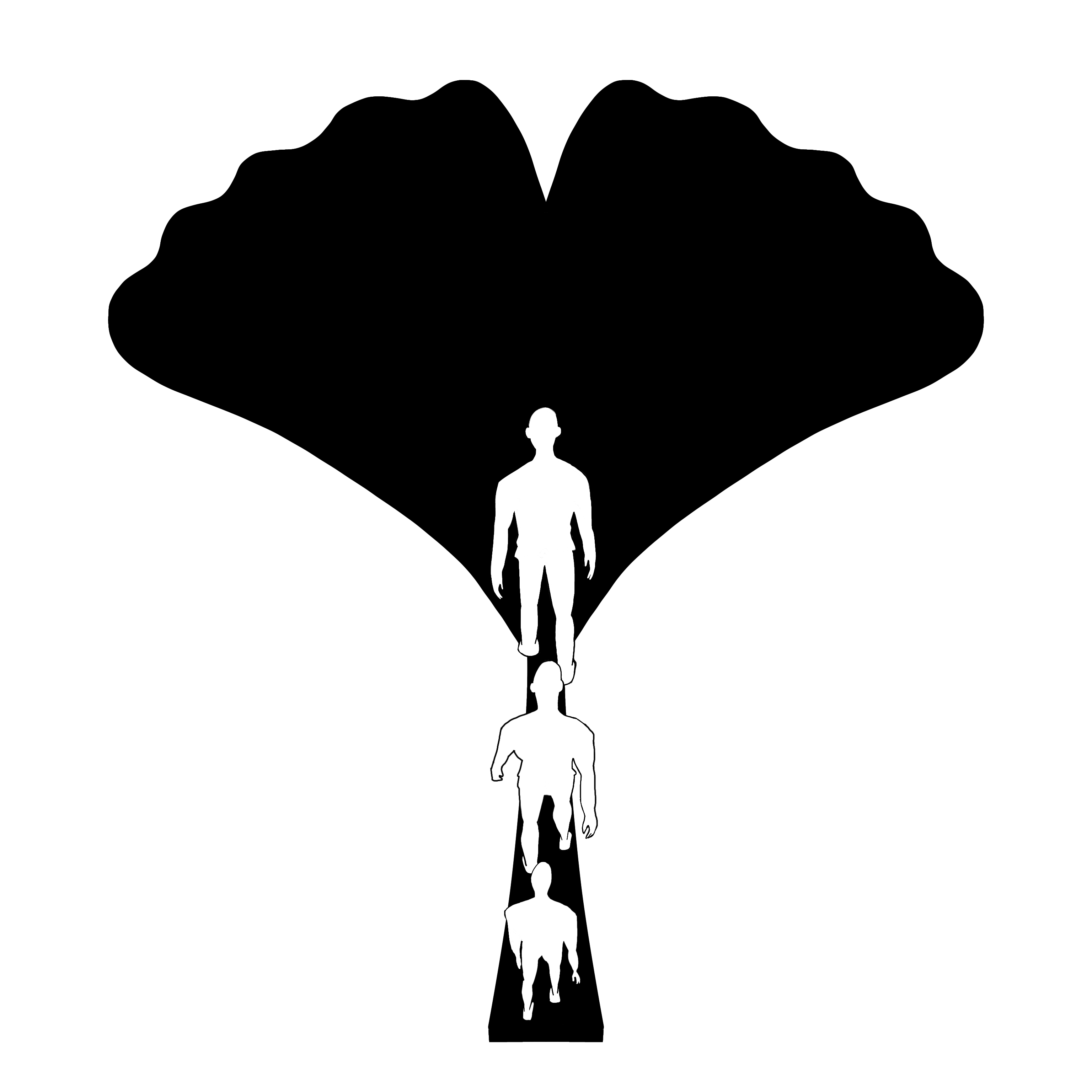
コメントを残す