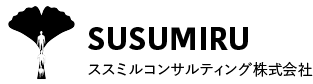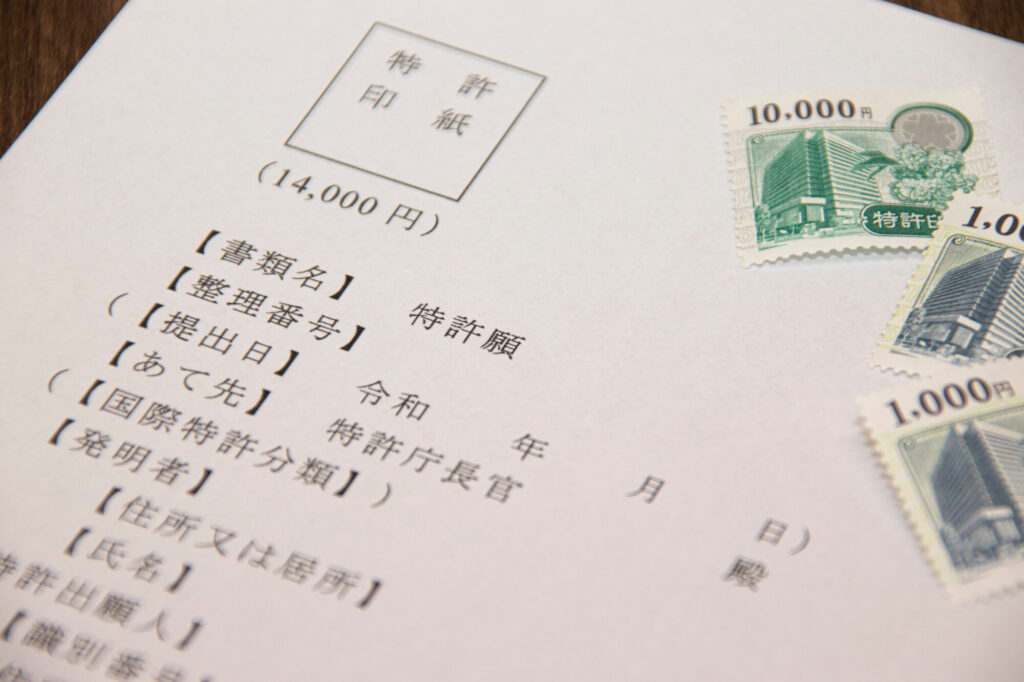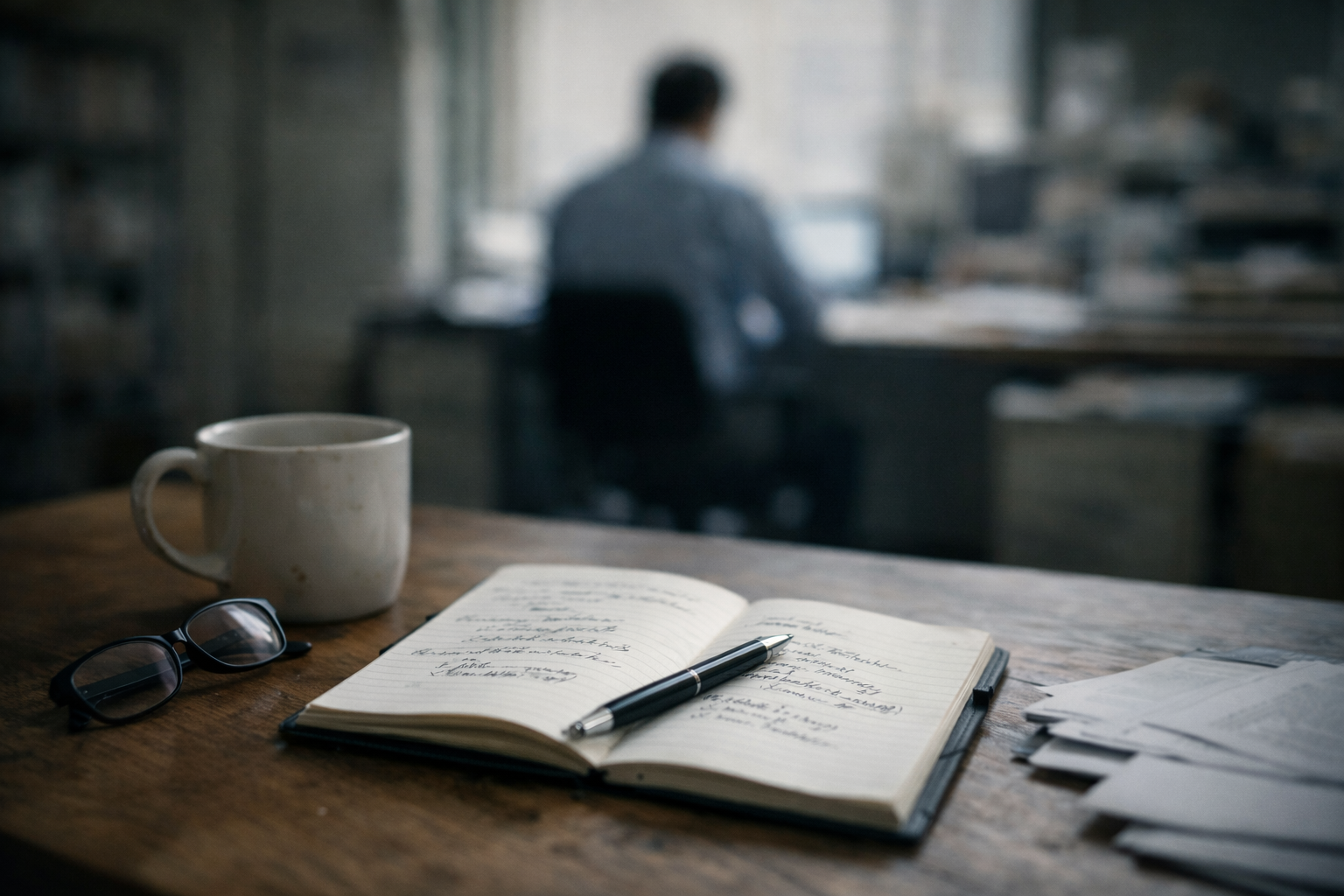「特許切れの情報って、ネットで調べれば出てくるんじゃないの?」
そんな声をよく耳にします。
確かに情報は公開されています――ただし、それは“探せばある”というレベルの話。
問題は、実務で使える状態になっているかどうかです。
◆ よく使われる情報源
公的データベースとして、J-PlatPat(日本)を活用することはできますが、開発したいジェネリック医薬品の、「特許がいつ切れるのか?」を特定するには、高度な知識と労力が必要です。
◆ 情報の「落とし穴」
- 延長登録の有無・内容が見えにくい
- 満了日が変更されている場合がある
- ブロック特許かどうかの判断が困難
- 同一成分に複数の特許がある場合、全体像の把握が難しい
さらに、海外メーカーとのビジネスを見据えた調査では、日本の特許と海外の状況を横断的に比較する必要も出てきます。
◆ 実務で求められるのは“加工された情報”
現場では次のようなニーズが頻繁に聞かれます:
- 「ジェネリック開発に向けて、特許の切れる成分を整理したい」
- 「今後XX年までに特許が満了する製品を一覧にして使いたい」
- 「将来の開発候補製品を特許状況から抽出したい」
つまり、単なる“情報”ではなく、“すぐ使える形に整理された情報”にこそ価値があるのです。