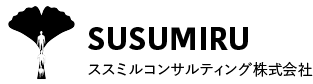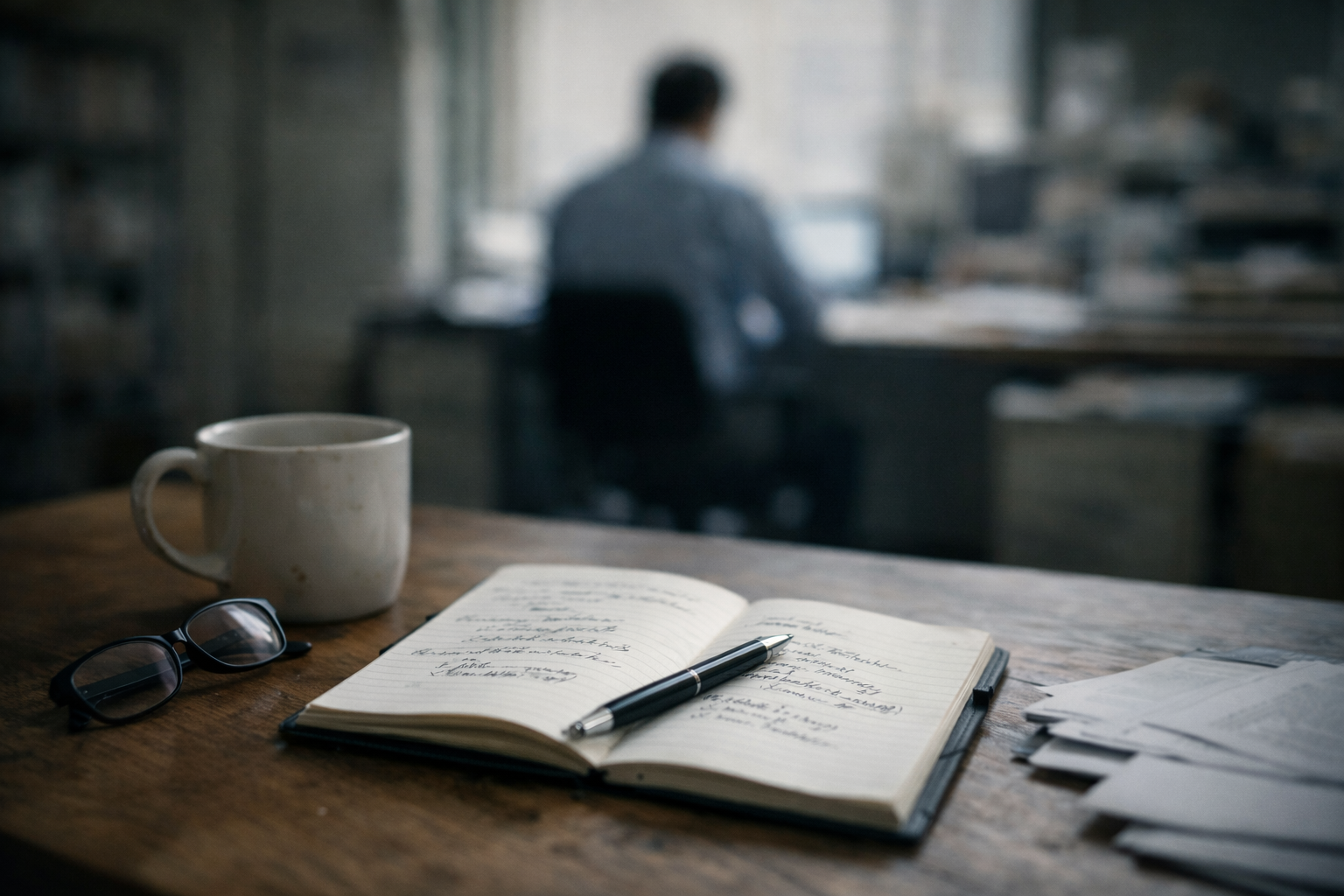最近、4月に開催されるCPHIのセミナー資料の作成が大詰めを迎えていて、ブログの投稿頻度が下がってしまっています。
今日は、先日テレビ朝日で放送された『タモリステーション』最新作では、南海トラフ地震をテーマに、「正しく恐れ、備える」という視点からさまざまな検証が行われていました。
その中でも特に印象に残ったのが、高知県黒潮町の話題です。
34.4メートル── 想定される津波の高さ
黒潮町は、南海トラフ地震によって最大34.4メートルの津波が襲うと想定されています。
まさに日本で最も大きな津波被害が想定されている地域の一つです。
この町では、津波避難タワーが整備され、住民の命を守る減災インフラとして機能しています。
番組内では、ご高齢の方がインタビューに答えており、「普段の散歩で、避難タワーに上っている」と語っていました。
この言葉に、私は深く心を打たれました。
「避難する」という行動を日常の中に取り入れる
災害時の行動というと、特別なものと捉えがちです。
しかし黒潮町では、避難行動そのものが“日常”の中に溶け込んでいるのです。
✅ 道を覚える
✅ 到着までの時間感覚を体で知る
✅ 避難場所を“身近な場所”にしておく
この「習慣化された行動」が、いざというときの落ち着きと確実な行動力に繋がるのでしょう。
一方で、私たちはどうか?
私自身も、「南海トラフ地震が起きるかもしれない」という危機感は持っています。
けれど、それが日々の行動に結びついているかといえば──正直、まだまだだと感じます。
多くの方も同じではないでしょうか?
知識としては知っているけれど、避難ルートを歩いたことがない。
避難先の確認も「なんとなく知っている」レベル。
訓練も「仕事があるから参加できない」という理由で後回しにしてしまう。
そんな中、黒潮町のように“習慣として身についている地域”があるということは、大きな学びです。
「正しく恐れ、備える」ことの大切さ
番組タイトルにあった「正しく恐れ、備える」。
これは、災害に対して必要以上に不安になるのではなく、事実を知り、行動に移すことの大切さを伝えている言葉だと感じました。
✔ 被害の大きさを具体的に知る
✔ それに対して何ができるかを考える
✔ そして、行動として実践する
たとえ小さなことでも、自分の体を使って体験することは記憶に残ります。
実際に歩いてみる、避難先に足を運んでみる、家族と話し合ってみる。
それらを積み重ねていくことで、いざという時に落ち着いて動けるのだと思います。
まとめ:災害を“知って終わり”にしない
南海トラフ地震のような巨大災害は、確率ではなく「いつ起きてもおかしくない未来」です。
大切なのは、情報を知っただけで満足せず、自分自身の行動として落とし込むこと。
黒潮町の住民のように、避難を“日常の一部”にすることで、きっと未来は変えられる。
私たちもできることから、一歩ずつ始めていきたいですね。
個人として、企業として、行動に繋げていきたいですね。