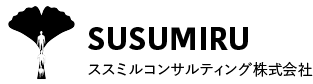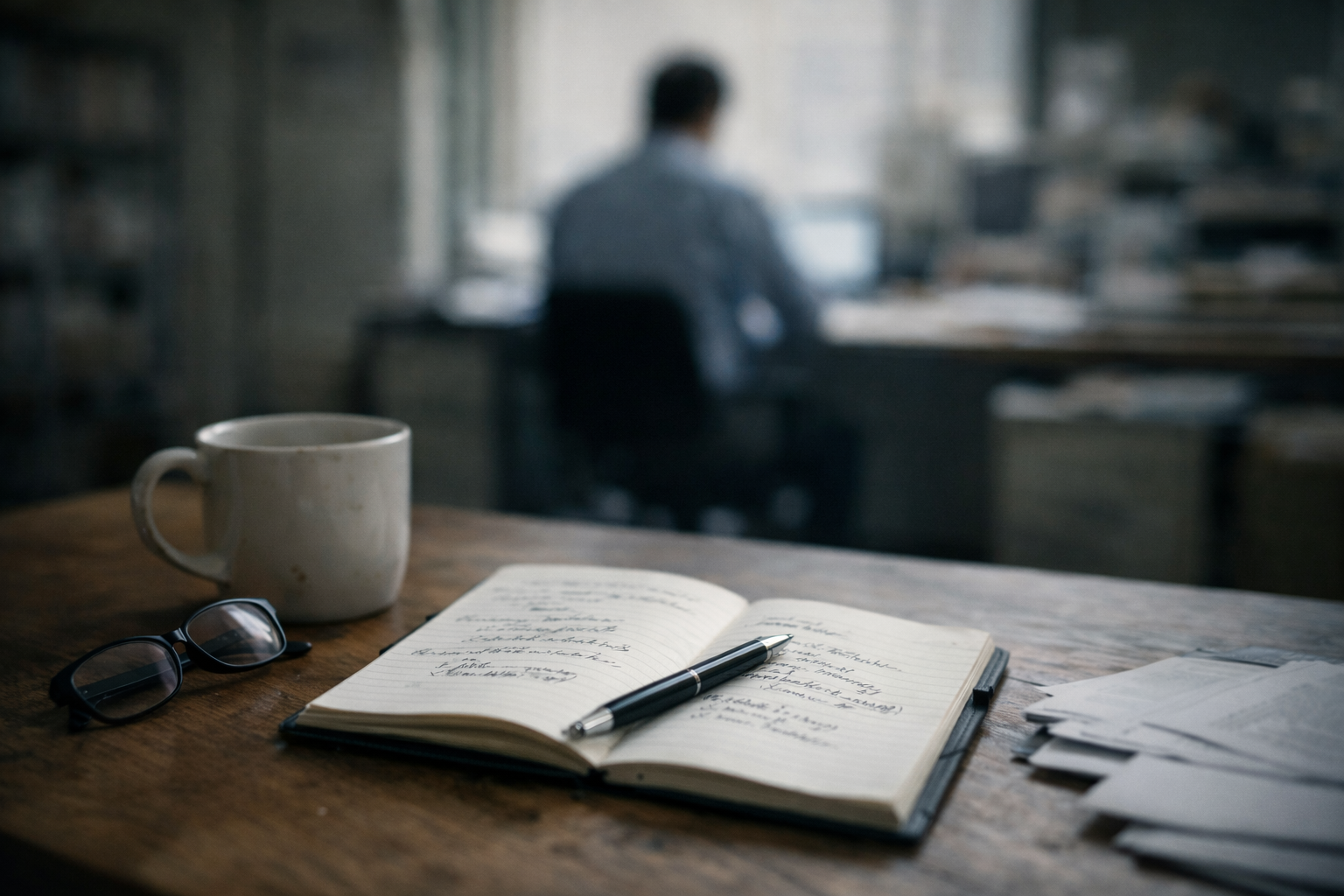南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、関西空港の耐震性や医薬品の輸入に与える影響について考えてみました。
関西空港のBCP(事業継続計画)についての資料を読み、さらに阪神淡路大震災の被害状況の文献を調査しました。
その結果、関西空港自体の被害は重要拠点として対策が取られており、被害が限定となる可能性が高いことがわかりました。
しかし、物流の要である本州側の交通インフラや製薬企業の事業継続性が課題となることを考える必要があると感じました。
1. 関西空港の耐震性と南海トラフ地震の影響
関西空港のハザードマップを確認すると、想定される震度は6弱。
阪神淡路大震災時の被害状況やその後のBCP対策を参考にすると、関西空港が大規模な損壊を受ける可能性は低いと考えられます。
関西空港のBCP対策資料によると、
✅ 耐震化された滑走路や施設
✅ 液状化対策の強化
✅ 緊急時の発電・通信対策
といった準備が進められています。
そのため、海外からの医薬品貨物は大きな遅延なく受け取ることができる可能性が高いと考えられます。
2. 課題となる「本州側の物流インフラ」
一方で、懸念されるのは関西空港から本州への輸送ルートです。
大阪市内も震度6弱の予測ですが、特に液状化のリスクが指摘されています。
港湾エリアや主要道路が影響を受けると、空港から医薬品を輸入者へ届ける物流が滞る可能性があります。
また、関西空港で働く方々の通勤も問題になりえます。
空港自体の機能が維持されていても、貨物の取り扱いや通関業務を行う人員が不足すると、結果的に物流の遅延につながる可能性があります。
3. 製薬企業・商社側のBCP対策
もう一つの課題は、医薬品を受け取る側の製薬企業や商社の事業継続です。
医薬品の輸入には、
✔ 通関手続き
✔ フォワーダーとの連携
✔ 在庫管理と配送手配
が必要ですが、これを行うオフィスや拠点が被災してしまうと、業務が滞ってしまいます。
そのため、多拠点化は有効な対策となります。
✅ 関西以外に事業拠点を設けることで、被災地外のオフィスで業務を継続できる。
✅ クラウド化によるデータ共有で、遠隔からでも貨物の受取手配が可能になる。
こうしたBCP対策を進めることで、南海トラフ地震の際にも医薬品の供給を止めることなく維持できる可能性が高まります。
4. まとめ ── 医薬品物流のリスクとBCP対策
関西空港自体は、南海トラフ地震でも大きな被害を受ける可能性は低いと考えられます。
しかし、本州側の交通インフラや輸入企業の機能維持が課題となります。
そのため、製薬企業や商社は多拠点化やデジタル化を進め、リスク分散を図ることが重要です。
災害時にも途切れない医薬品供給を目指して、今からできる対策を考えていきましょう。
📩 お問い合わせ
ススミルコンサルティング株式会社
📧 お問い合わせフォーム