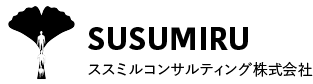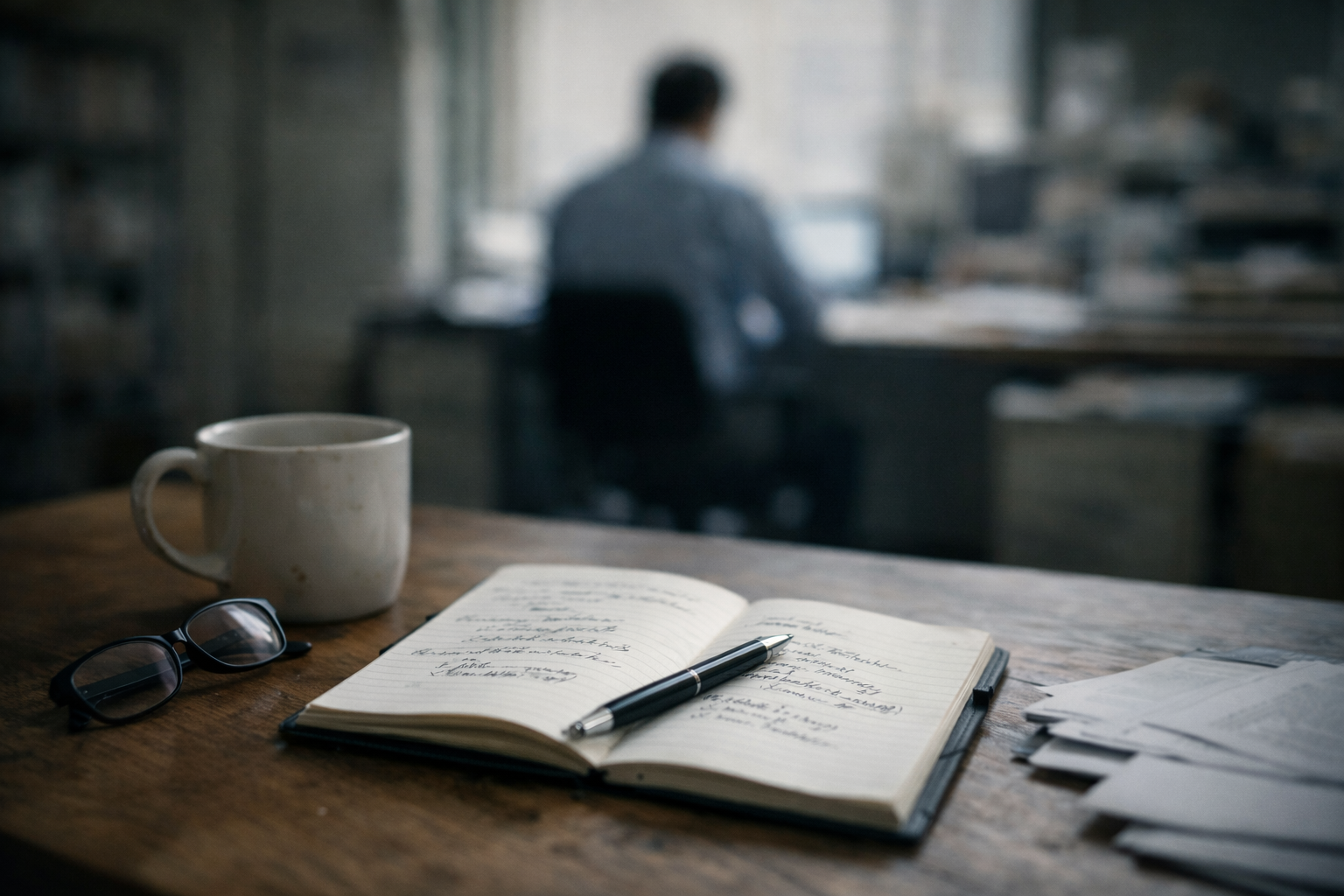先日ご紹介した、京都府舞鶴市の「シベリア引揚記念館」。
そこでは、かつて戦争体験を直接語ってきた語り部の方々が高齢となり、
現役で語れる人はほとんどいなくなりました。
代わりに、過去の証言映像とAIを組み合わせた新たな“語り部”が誕生しています。
来館者が質問すると、該当部分の証言映像が再生され、
まるでその人と対話しているかのように感じられる仕組みです。
記憶を、温度をもって未来へ渡すための工夫に、心を動かされました。
広島市立基町高校の「原爆の絵」もまた、記憶を未来へ託す活動です。
創造表現コースの生徒たちは、被爆者の方から直接話を聞き、
その証言をもとに半年から一年かけて絵を描きます。
声の震え、沈黙、目の奥に宿る光景まで想像しながら、色や形で表現していきます。
そこには炎や廃墟の風景だけでなく、水を求めてさまよう人、遠くで呼びかける声、
静まり返った街の空気など、語りの中に宿る細やかな情景が込められています。
やがて被爆者の方々も高齢となり、この直接のやり取りは叶わなくなるでしょう。
その時、「原爆の絵」は次の世代の語り部として生き続けます。
舞鶴のAI語り部が映像と言葉で、基町高校の作品が色と形で──
それぞれ異なる方法で、過去の記憶を未来へつなぎます。
語り継ぐという行為は、形を変えても、その根にある願いは同じです。
「忘れないでほしい」という祈りと、「感じてほしい」という願い。
それを受け取った私たちが、さらに次の世代へ手渡していくことこそが、平和の礎となります。
そして、こうした活動に若い世代が真剣に取り組んでいることに、深く心を打たれます。
そのまっすぐな眼差しは、私たち大人にとっても学びの源です。