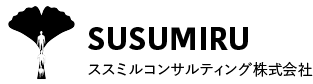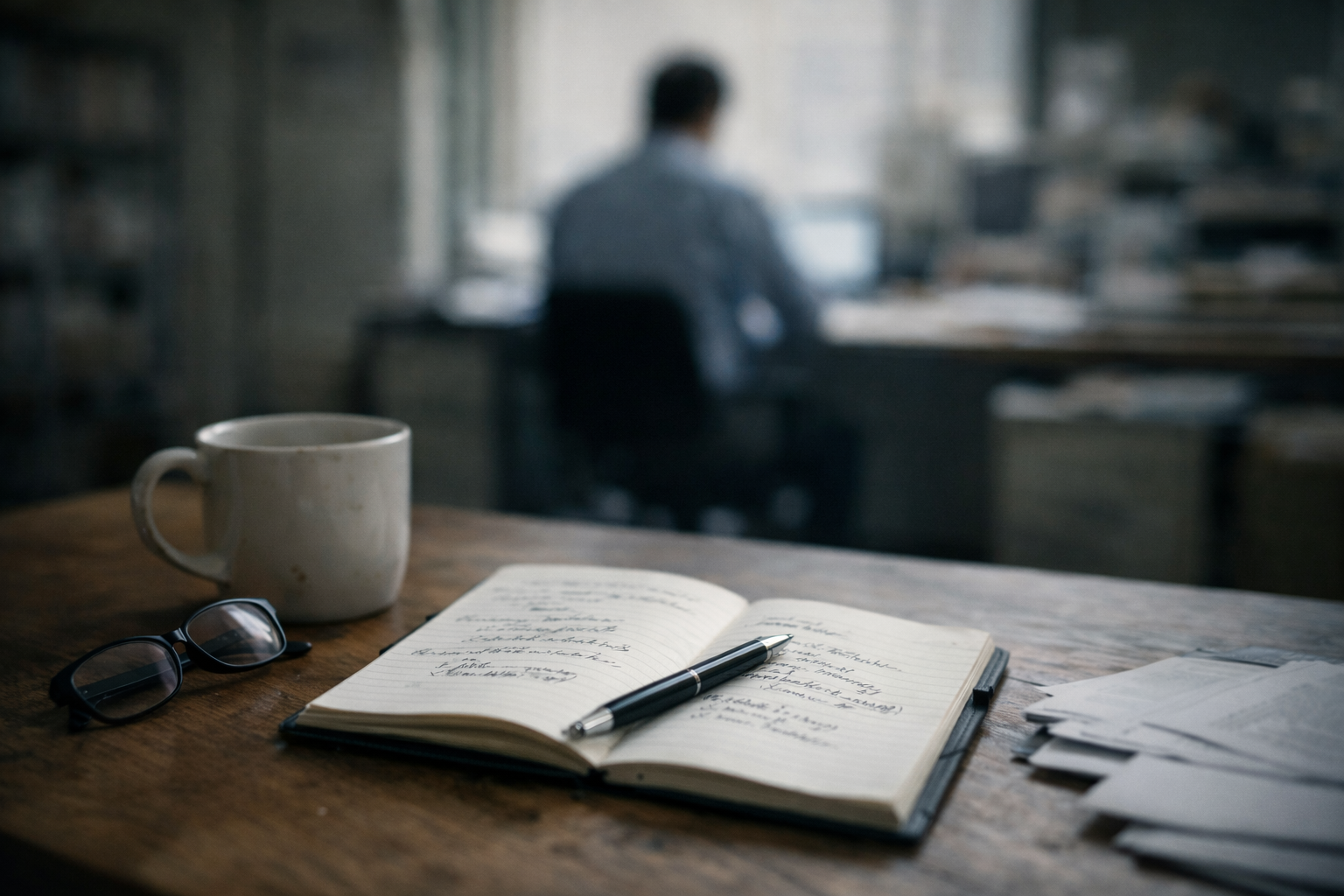「ねえ、この薬って効くのかな?」
夕飯後、娘がふと差し出してきたのは、いつもの薬と違う名前のシートだった。
どうやら、処方薬の在庫が切れていて、別のものに変更されたらしい。
ただの銘柄変更かと思ったら、そうではなかった。
成分ごと違っていた。
「いつものが、もう手に入らなくて」
薬剤師さんの説明を、娘は不安そうに反芻していた。
今年の「骨太の方針2025」にも、薬の供給について触れられている。
医薬品の安定供給に向け、抗菌薬等のサプライチェーンの強靱化や、基礎的な医薬品等の供給不安に対応する。
でも、私たちの暮らしに届くのは、
「サプライチェーンの強靱化」という言葉ではなく、
“薬が変わった”という、小さな不安だった。
私は原薬の調達や、製薬企業と現場のあいだをつなぐコンサルの仕事をしている。
医薬品は、一見「モノ」だけれど、
実際には「時間」と「予測」と「制度」の上にようやく存在しているものだ。
ある製薬企業では、今まさに「この薬は作り続けるべきか」を検討している。
理由はシンプルで、採算が合わない。
流通コストが上がり、材料の価格も上がり、人件費も上がっている。
でも薬価は上がらない。
つまり、「必要な薬」が「製造できない薬」になってしまう。
薬の供給不足は、突発的に起きているように見えるけれど、
実は“静かに積もった合理化”の先にある。
少量・多品目の負担
不採算品の撤退
規制強化と製造リスクの高まり
そして、誰もが予測できなかったコロナと感染症の波
こうした積み重ねが、
ある日ふと、「これ効くのかな?」という不安になって、
家庭に届いてくる。
骨太方針には、こうも書かれている。
感染症の流行による需要の急激な増加といったリスクへの対策を講じる。
その“対策”を現場に落とし込むには、
ただの在庫積み増しでも、企業任せでも足りない。
医薬品の供給体制を考えるには、
それが「国家の安全保障」であると同時に、
「家庭の安心」に直結しているという視点が必要だ。
あのとき娘が手にしていた薬。
「効くかな」という不安は、薬のせいだけじゃなかったのかもしれない。
いつもの薬が、明日も届くとは限らない。
そんな時代だからこそ、
私たちは“供給”という目に見えにくいインフラに、もう少し意識を向けていく必要があると考える。