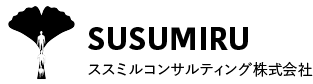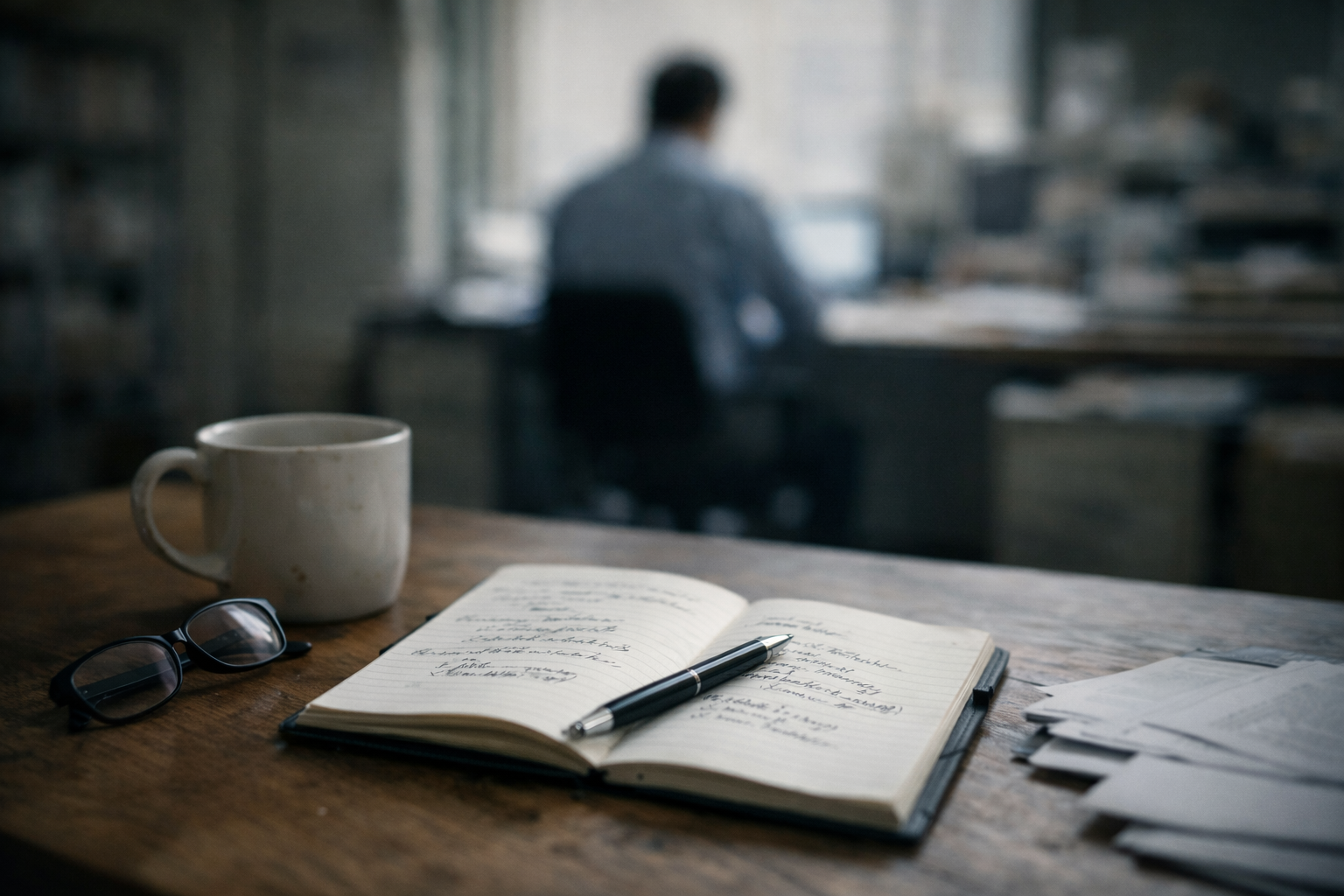2025年4月14日、ロイターが報じたニュースによると、
アメリカ政府が医薬品に対する関税の導入を検討し、正式な調査に着手したとのことです。
医薬品、原薬、中間体が調査対象に含まれるとされており、
その動きは、世界の医薬品供給構造に少なからず影響を与えるものになるかもしれません。
📊 データが示す“依存構造”の実態
昨日のブログでも触れましたが、
アメリカに登録されている**DMF(Drug Master File)**を国別に見てみると、
- インド:49%
- 中国:21%
- アメリカ(自国):9%
という構成になっています。
つまり、アメリカは自国よりも圧倒的にインド・中国からの供給に依存していることが分かります。
💡安易な関税導入にはリスクも
この構造を踏まえると、
アメリカが医薬品に対して一律で関税をかけることは、
患者や保険会社の負担増につながり、治療の継続性にも影響する可能性があります。
特に、安価なジェネリックや安定確保医薬品にまで関税が及ぶようなことがあれば、
命に関わる“治療の選択肢”が狭まる懸念も生じてきます。
一方で、治療上の有用性が高くない医薬品や、
過度に価格競争が行われている薬剤を整理し、使用量を抑える方向に舵を切るという見方もできます。
また、アメリカ国内での製剤工場の誘致や再稼働といった政策も、ごく一部で進むかもしれません。
🔁 対中関税との連動、そして“選別”の関税へ?
今後考えられるのは、
一律ではなく、「特定国(たとえば中国)からの製剤や原薬」に限定した選別的な関税措置です。
これは、いわゆる報復関税の応酬の一環として用いられる可能性もあり、
対象の範囲・理由・時期によっては、グローバル供給網に波紋を広げるでしょう。
🌏 日本市場への“静かなシフト”も視野に
このようなアメリカの市場環境の不安定化が進んだ場合、
逆に「日本市場へ製品を販売したい」と考える企業が増える可能性もあります。
価格や数量の調整が難しいアメリカ市場よりも、
品質基準が高く、長期的な関係構築が重視される日本市場に魅力を感じる海外サプライヤーが出てくることは十分に考えられます。
特に、中堅クラスのインド・中国メーカーにとっては、
新たな市場としての“日本再注目”が起こる兆しとも言えます。
👀 今、私たちにできること
日本の製薬業界、商社、輸入企業にとって、
この流れはリスクであると同時に、チャンスでもあります。
- 情報を注視しながら、いち早く動向を掴むこと
- サプライヤーとの会話に“データ視点”を持ち込むこと
- 市場の変化に対して、自社の調達戦略を柔軟に見直すこと
こういった姿勢が、これからの数年を左右する鍵になるかもしれません。
データは、流れを読むヒントになる。
そのヒントをどう活かすかは、私たち次第。
これからも、こうした動きに注視しながら、次の一手を探っていきましょう。