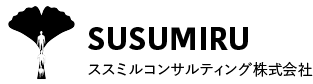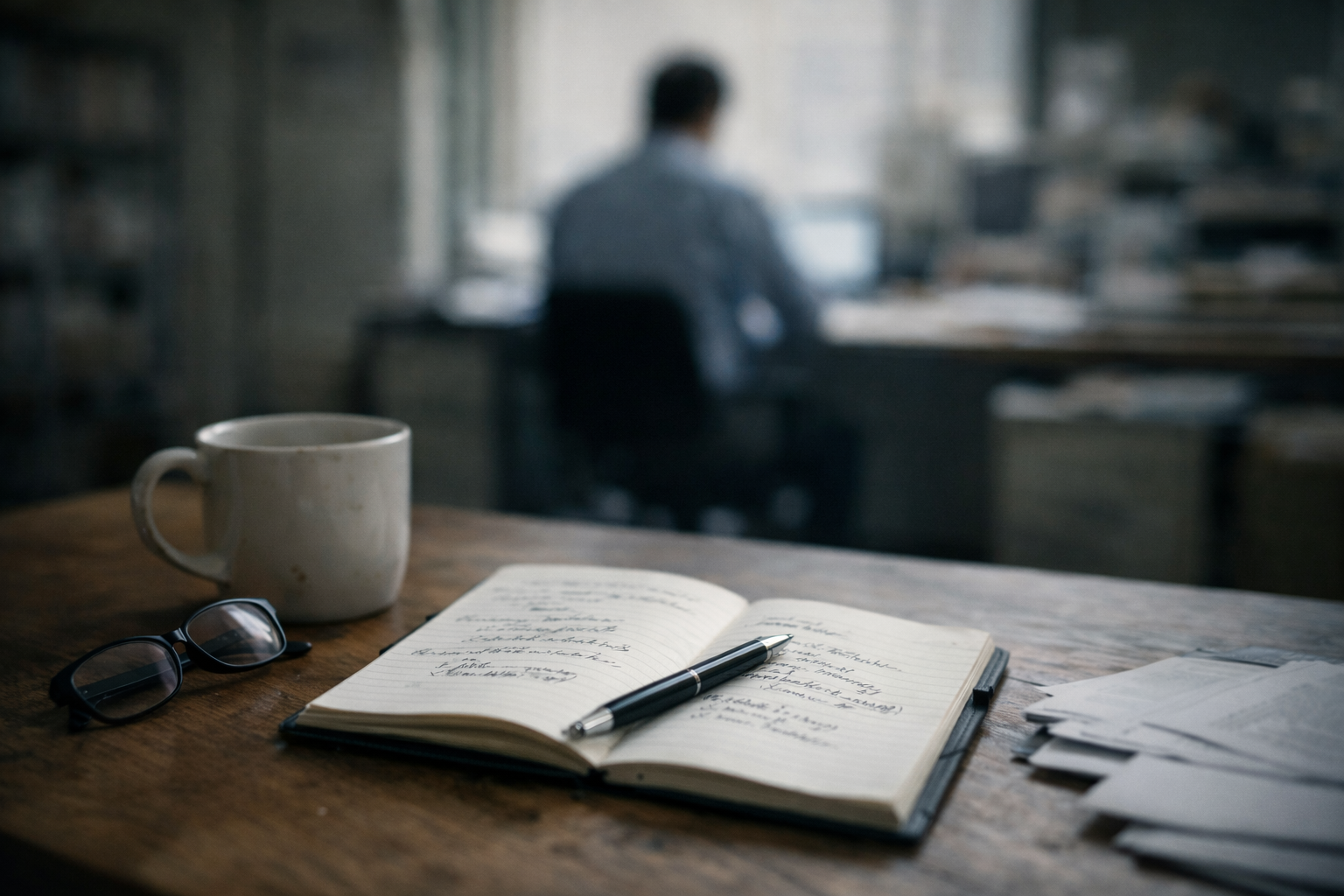2025年6月、「骨太の方針2025」が公表されました。
そして、翌月に行われた参議院選挙では、自民党が大敗を喫しました。
政策の継続性や優先順位への影響などについてはどうなるのでしょうか。
選挙で変わるのは、議席の数だけではありません。
政権の「力のかけ方」、官僚の判断基準、そして予算のつく先――
こうした軸足そのものが変わる可能性があります。
だからこそ、今は静観ではなく、「声を届ける」べきタイミングではないかと思います。
医薬品産業は、どこへ向かうのか
骨太の方針2025では、医薬品関連に関して以下のような項目が盛り込まれました:
- サプライチェーンの強靭化と安定供給体制の整備
- 創薬エコシステムの発展とファースト・イン・ヒューマン試験施設の整備
- バイオ医薬品やプログラム医療機器を含む製造体制と人材確保
- バイオシミラーの国内生産・人材育成・使用促進
- 抗菌薬など基礎的医薬品の供給不安対応
- セルフケア推進に向けたOTC化と自己負担の見直し検討
いずれも重要なテーマであり、「日本の医療の未来をどう守るか」という国家的な意思が垣間見えます。
一方で、日々製薬企業の購買部門や医薬品商社と接している私から見れば、
こうした政策と“現場の実情”の間に、決して小さくないギャップがあると感じます。
声なき現場の課題
たとえば、「原薬の国内回帰」「複数製造拠点の構築」はもっともらしく聞こえます。
しかし現実には、コストや品質保証体制、医薬品添加剤の販売中止などの問題で
安定供給体制を整えるどころか、後退していることもあります。
こうした声は、政策の文章の中には現れにくい。
だからこそ、“翻訳者”のような役割が必要なのです。
現場から、誰が言語化するか
現場で起きていることを、言葉にする。
その言葉を、業界団体や行政、地域のステークホルダーに届けていく。
たとえ小さな動きでも、そうした積み重ねが、政策の方向や“予算の届く場所”を変えていきます。
骨太の方針が語る未来像が、現実の現場に根を張るには、
誰かが“今の課題”を可視化し、提案しなければなりません。
ススミルでは、こうした「翻訳と提案」の活動にも微力ながら取り組んでいきたいと考えています。
最後に
医薬品産業は、人の命と健康に直結します。
制度設計や戦略の一つひとつが、患者さんに届く薬の選択肢を左右します。
政策と現場の間には、解像度の差がある。
しかし、諦めずに発信する必要がある。
私はそう思うのです。
医薬品の安定供給に支障を来し兼ねない課題について、どう発信してよいかわからない。
それでも、発信し続けてください。
差し支えなければ、その声をススミルコンサルティングにお伝えください。