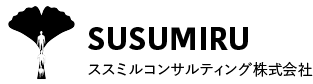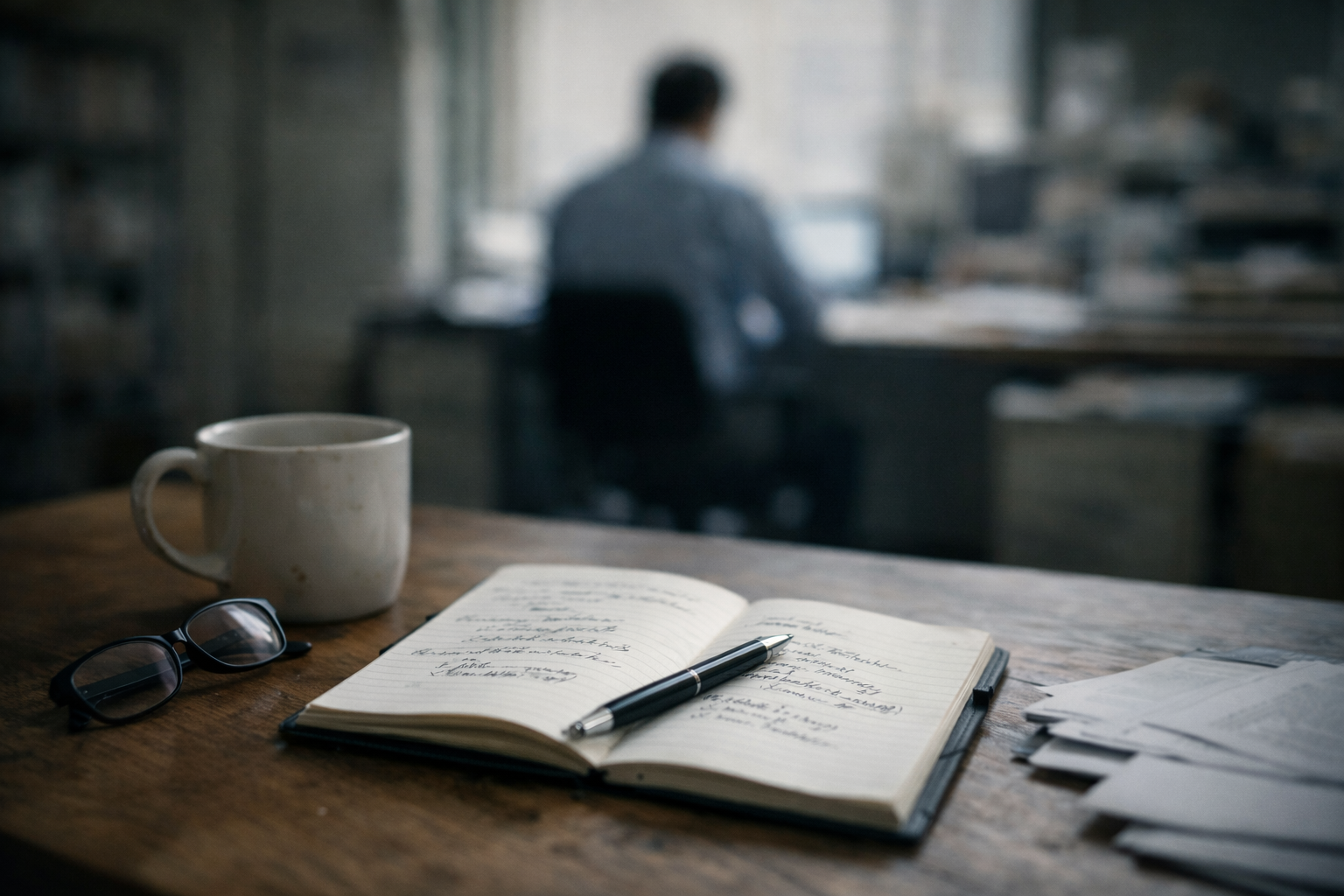6月2日、アイリスオーヤマが「備蓄米」の家庭向け販売を開始することが、
今朝のニュースになっていました。
また、農林水産省が行った備蓄米の随意契約説明会には、
全国からなんと320社以上が参加したとも報道されていました。
いま、これまでとは異なる“お米の流れ”に、
多くの関心が集まっています。
この備蓄米の放出は、この春からすでに始まっていました。
しかし、それが一般消費者の手に届くことは少なく、
仮に届いたとしても、価格は昨年の2倍以上という状況でした。
今回の取り組みが注目されたのは、
「誰が」「いくらで」「どのように」消費者に届けるのか、
その流通の仕組みごと見直そうとしているからだと感じます。
このニュースを目にしたとき、
ふと頭をよぎったのが、2005年に施行された「医薬品マスターファイル制度」のことでした。
医薬品の原材料、特に原薬の流通構造を大きく変えた、
いわば業界の“転換点”とも言える制度です。
気がつけば、あれからもう20年になるのですね。
制度導入以前、海外製造所でつくられた原薬は、
複数の商社が介在しながら国内製薬企業に届けられることもありました。
そこに導入されたのが、マスターファイル制度。
これにより、医薬品商社は原薬のマスターファイル登録業者となり、
厚労省にマスターファイルを提出する会社が増えました。
商社は、試験や品質保証の体制を整え、
中には自社で試験室を持つところも出てきました。
それはまるで、“信頼を証明する資格”のような意味を持ち始めたのです。
その結果、
かつて複雑だった輸入原薬の流通は、
次第にシンプルに、そして透明に変化していきました。
私はあの流れを、今回の備蓄米の動きと重ねてしまいました。
これまでの流通ルートでは、
本当に届けたい相手に届かない。
価格も見えづらく、動きも遅い。
だからこそ、新しい手段が必要になる。
それは単なる「商品」の話ではなく、
「仕組み」そのものを見直す動きになるのかもしれません。
医薬品原材料の流通も、
そして私たちの暮らしの中にある他のものも、
おそらく今、再び“流れのかたち”が問われているのだと思います。
このブログではしばらく、
医薬品の流通の歴史や、いま起きている変化について、
少しずつ書いていこうと思います。
また次回も、どうぞお付き合いください。