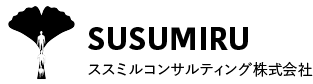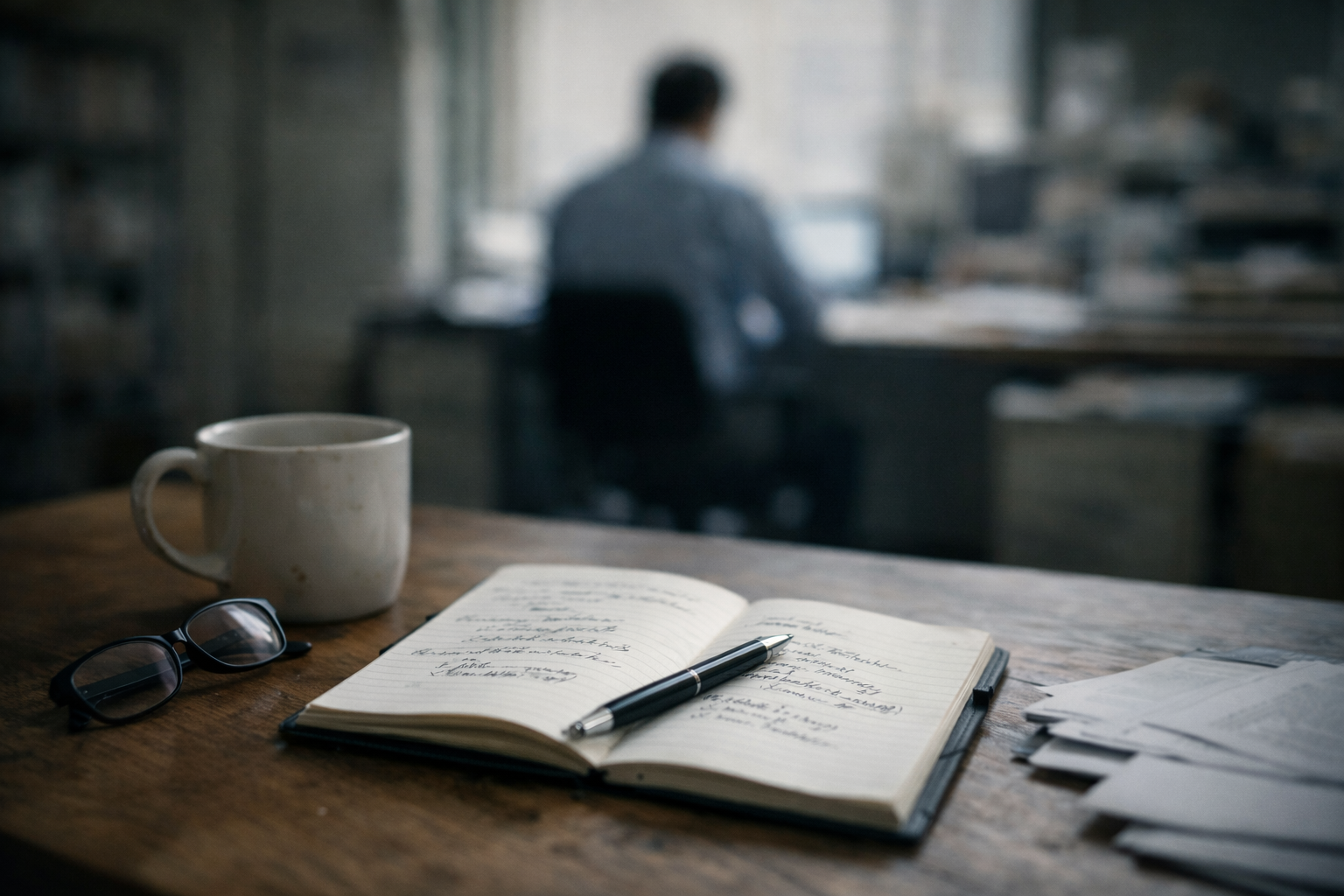今日は東日本大震災から14年の節目となります。
この機会に、今後30年以内に80%の確率で発生するといわれる南海トラフ地震が発生した際の通信環境について考えてみました。
今回の内容は、内閣府が公表している令和元年のデータをもとにしています。
南海トラフ地震発生時の通信環境
現在公表されているデータによると、電力や通信の復旧には一定の時間がかかると想定されています。
電力の復旧見込み
- 1~2週間程度で復旧
通信の復旧見込み
- 固定電話
- 四国地方:4週間
- 近畿・東海地方:数日~1〜2週間
- 携帯電話
- 四国地方:3週間
- 近畿・東海地方:数日~1週間
スマートフォンの普及や、企業・自治体のデジタル化が進む中、通信や電力に障害が発生した場合の影響は東日本大震災の時以上に大きくなると考えられます。
進められている通信インフラの対策
一方で、こうしたリスクに対応するための取り組みも進んでいます。例えば、
✅ 通信基地局への非常電源の迅速な供給
✅ 船舶基地局の設置によるエリアカバー
✅ 基地局の耐震化や、被害が少ない場所への設置
これらの対策によって、被災後の通信環境の回復がどの程度早まるのか、今後の調査結果が待たれます。
国は現在、南海トラフ地震の被害想定の見直しを計画しており、1~2年以内には新たなデータが公表されると考えられます。
今、何をしておくべきか?
「では、今のうちに何をしておけばいいのか?」と考えた方もいるかもしれません。
現時点でのリスク軽減策として、アナログの活用と多拠点化を意識することが重要です。
個人でできる対策
✅ 情報収集手段を確保する
・バックアップ電源(モバイルバッテリー・ソーラーチャージャーなど)
・ラジオ(通信障害時でも災害情報を取得できる)
・固定電話や公衆電話の活用(携帯よりも繋がりやすい)
企業が考えるべき対策
✅ 多拠点化によるリスク分散
・災害発生地域とは別の場所に拠点を持ち、事業継続性を高める
・デジタル化が進んだ現在、東日本大震災の時よりもその重要性は増している
✅ 紙媒体を活用した業務継続策
・重要な業務を短期間でも遂行できる体制を整える
・一時的に拠点を移すことを想定(リモートワークの活用)
✅ モバイルPC・クラウド活用の推進
・モバイル端末を活用し、どこでも業務ができる環境を整備
・業務データをクラウド化し、拠点が被災してもアクセスできるようにする
新型コロナ感染症の際、リモートワークが普及しました。
あの経験を活かして、企業としても「災害時にどう事業を継続するか?」を考えておく必要があります。
減災対策のご相談はススミルコンサルティングへ
弊社では、企業ごとに最適な減災対策のコンサルティングを行っています。
「自社でどのような対策を取ればいいか?」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
📩 お問い合わせ先
ススミルコンサルティング株式会社
お問い合わせフォーム
災害に備え、今からできることを一緒に考えていきましょう。