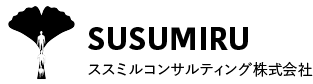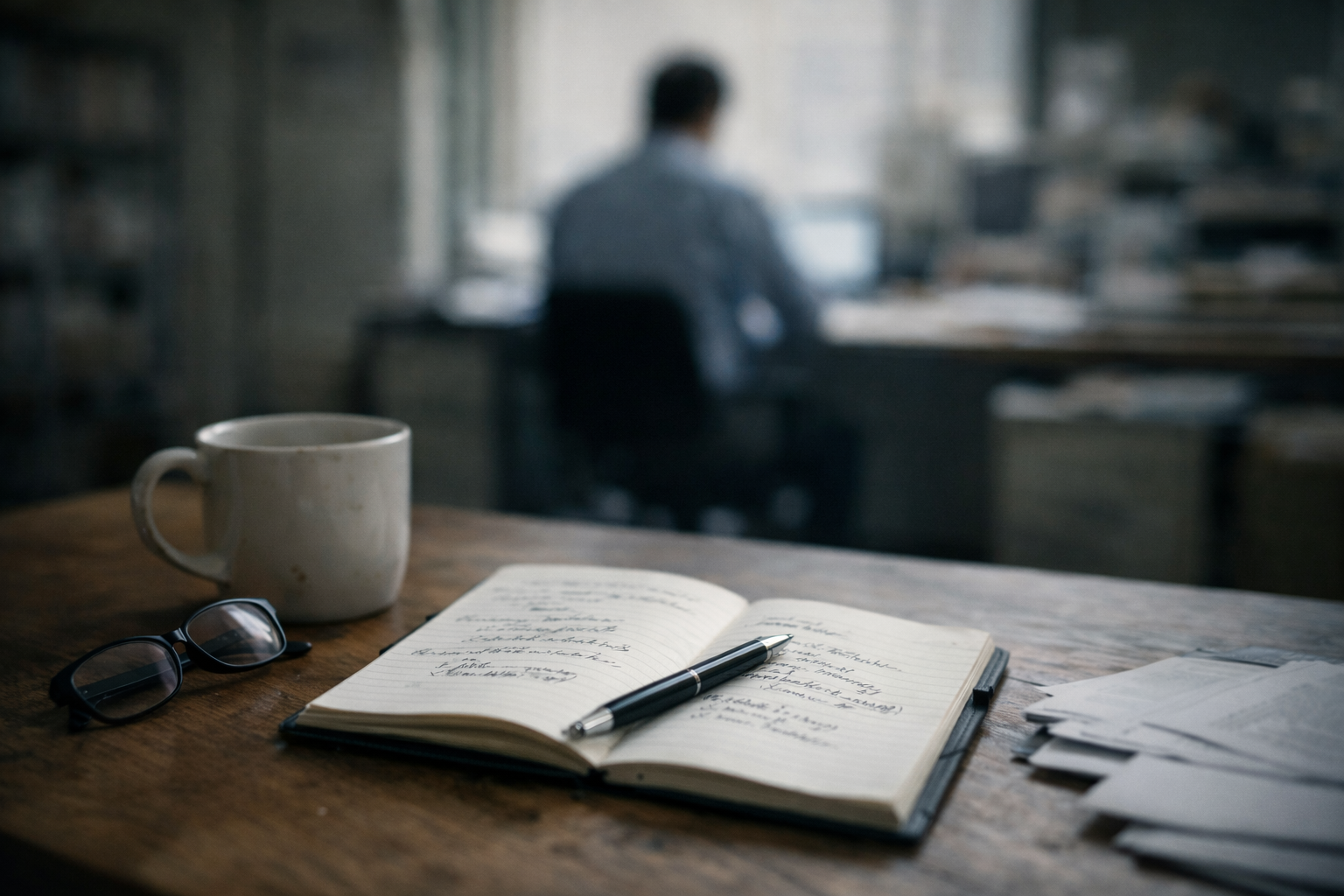昨日、ある医薬品が自主回収されるという発表がありました。
製品は「ランソプラゾールOD錠30mg『トーワ』」。
回収理由は、製造販売承認書に記載されていない製造所の原薬が使用されていたというものです。
製品そのものは品質規格に適合し、健康被害の報告もなく、クラスⅡに該当する回収とされています。
それでもこのような事象が起きた背景には、“構造的リスク”**があるのではないかと、私は感じています。
■なぜ、こうしたことが起こるのか?
公開されている情報からの仮説ですが、同剤の別規格では当該原薬製造所の記載が承認書にあり、
実際に使用されているとのこと。この内容からおそらく15mgOD錠で使用している原薬を
30mgOD錠に使用したのではないかと感じました。
■どのようなときに、こうしたリスクが発生するのか?
実務上、同じOD錠のため、分けずに管理しているケースは珍しくありません。
一方で、含量が異なることや、剤形が異なることで、溶出性や安定性の違いによって、
同じ製剤でも使用できる原薬製造所が異なることもあります。
このような状況下で、
- 両含量が同じマスタデータで一元管理されている
- システムでは同一コードで管理されているが、承認書レベルでは分かれている
といったギャップがあると、人の判断に依存した運用が生まれやすくなります。
この「人が気をつけていれば防げた」という構造こそが、リスクとなります。
■では、どう対処するか?
✅ 1. 原薬が共通化できる場合
同一の原薬製造所で各剤形の承認を取得できるよう、可能な範囲で“努める”ことが望ましいと考えます。
ただし、これは安易な共通化を推奨するものではありません。
剤形が異なれば、成分の溶出や製剤の安定性に影響が出る可能性があるため、データに基づく対応が前提です。
共通化ありきではなく、「リスクと実行可能性のバランス」が重要です。
✅ 2. 原薬が異なる、または承認記載が異なる場合
- マスタを完全に分ける。
- 15mgOD錠用、30mgOD錠用と明確にマスタ名を分け、管理コードも別に設定する。
- 人の目でも識別できるようにし、“似ているけれど違うもの”を“違うものとして扱う”運用に徹する。
✅ 3. 特に注意すべきタイミング
- 新しい原薬製造所を追加する際
- 承認書から既存の製造所を削除する際
このような時期は特に、システムマスタの変更と承認書の記載がズレやすいため、
事前の確認・社内共有・実運用のルール化が重要です。
■調達・薬事・品質の部門にできること
このようなリスクは、どの会社にも潜んでいます。
だからこそ、今回のような事例を「他山の石」として終わらせず、
「わが社ではどうか?」と立ち止まって点検する機会にしていただけたらと思います。
調達部門の皆さんは、今一度こう問い直してみてください:
- 自社の原薬マスタは、剤形ごとに分かれているか?
- 管理コードや品名に、判別可能な仕組みがあるか?
- 誰が、いつ、どういうルールで変更を確認しているか?
■結びに
医薬品は、品質や有効性だけでなく、「ちゃんと守られている」ことへの信頼で成り立っています。
構造的なリスクを見つけ、仕組みで防ぐこと。
それが、安定供給と信頼を支える土台になるのだと、あらためて感じています。