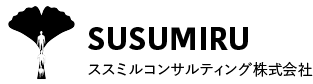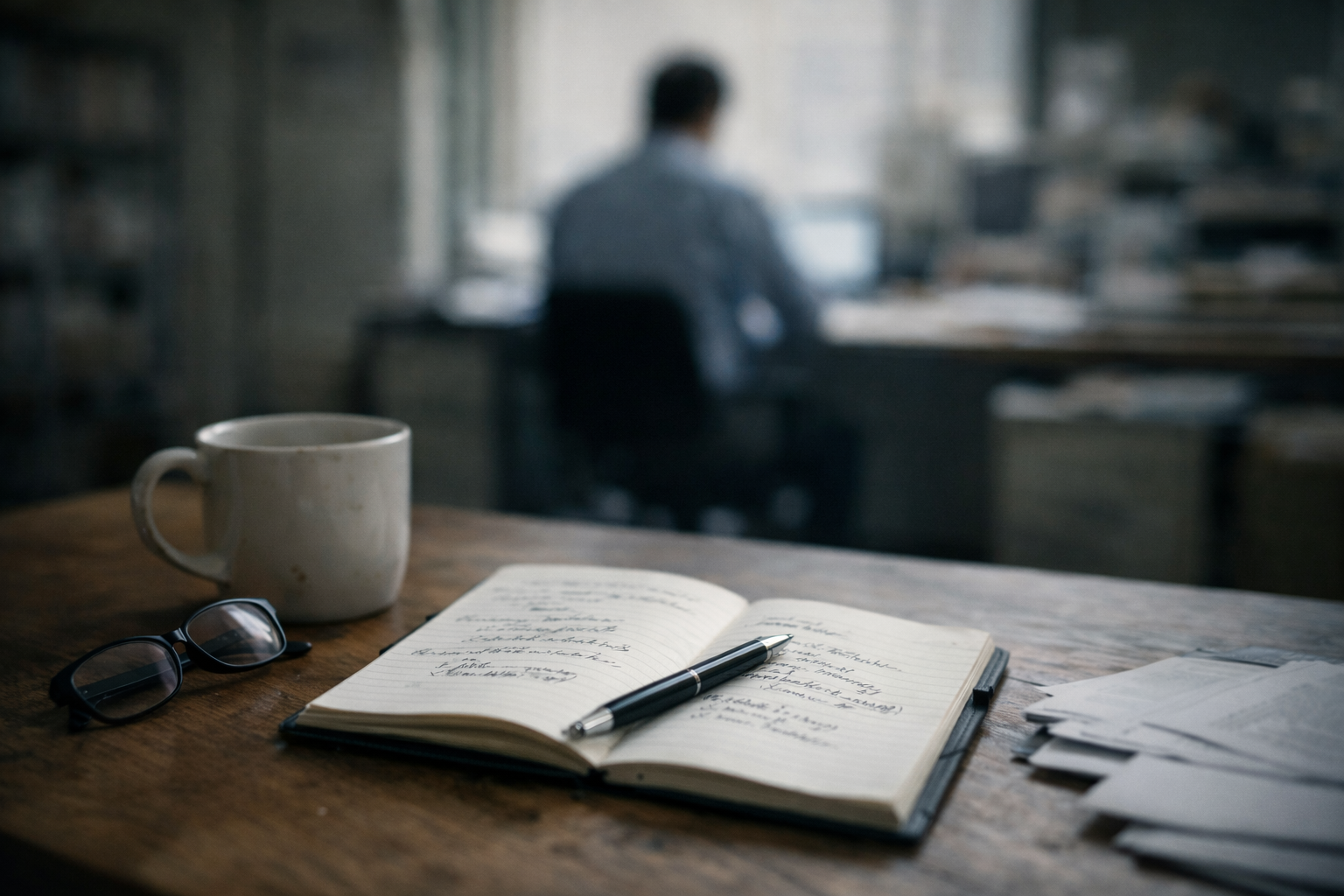はじめに
南海トラフ・都市直下型大地震は、日本にとって避けて通れないリスクのひとつです。企業の運営や社会全体のインフラに大きな影響を及ぼす可能性があるため、事前の備えが非常に重要になります。本記事では、災害発生時における事業継続計画(BCP)の一環として、携帯キャリアが進める災害対策に焦点を当て、企業が取るべき行動について考えます。
携帯キャリアが進める災害対策
https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2024/12/18_00.html
大規模災害発生時におけるネットワークの早期復旧に向けた通信事業者間の協力体制を強化
-各社のアセットの共同利用や船上基地局を活用- NTTドコモHPより引用
通信大手4社の NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、大規模災害の発生時におけるネットワークの早期復旧を目的として、通信事業者間の新たな協力体制を構築し、2024年12月1日から共同で運用を開始しました
協力体制の内容
1.通信事業者のアセットの共同利用による復旧活動
各社が保有するアセット(事業所、宿泊場所、資材置き場、給油拠点など)を共同で利用することで、被災地のネットワークの復旧活動を相互に支援し、早期復旧につなげます。
2.NTTグループおよびKDDI株式会社が保有する船舶の活用
NTTグループおよびKDDI株式会社が保有する船舶の活用携帯キャリア各社は、災害時に備えたネットワークの強化やバックアップシステムの整備を進めています。NTTグループとKDDI株式会社が保有する船舶に、ソフトバンク株式会社と楽天モバイル株式会社の船上基地局の設置が可能になり、海側からエリア復旧が可能な沿岸地域に対して携帯電話サービスを提供することで、被災地におけるモバイルネットワークの早期復旧に寄与します。
3.モバイル通信事業者と固定通信事業者の連携強化
モバイル通信事業者と固定通信事業者は連携を強化し、被害状況の把握やネットワークの復旧に必要な設備情報などの共有を通じ、自治体や病院などの重要拠点をカバーするネットワークの障害の原因となる固定通信網の支障箇所を特定するなど、復旧作業における優先順位を明確化します。
特に携帯電話基地局向けの回線の復旧を迅速化することで、被災地のモバイルネットワークを、これまで以上に早期に復旧できるよう取り組みます。
興味深いのは、NTTの災害対策室 室長を務める森田公剛氏のコメントです。この協定を「アセットを自社に限るのではなく、通信事業者全体が1つの企業として取り組む」仕組みだと語る。
こうした取り組みを理解し、企業も積極的に情報収集を行うことが大切です。
企業が今、取るべき一歩
企業は、次のような具体的なアクションを取ることで、より実践的なBCPを構築できます。
- リスク評価とシナリオの策定: 自社の立地や事業特性に合わせたリスク評価を行い、最悪のシナリオを想定する。
- 低震度地域の情報収集: 震度分布データを活用し、避難先や臨時拠点の候補地を検討する。
- 訓練とシミュレーション: 定期的な避難訓練や通信テストを行い、実際の災害時に備える。
これらの対策を実施することで、企業は災害時のリスクを軽減し、より強靭な事業運営を目指すことができます。