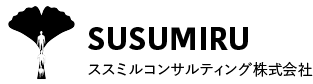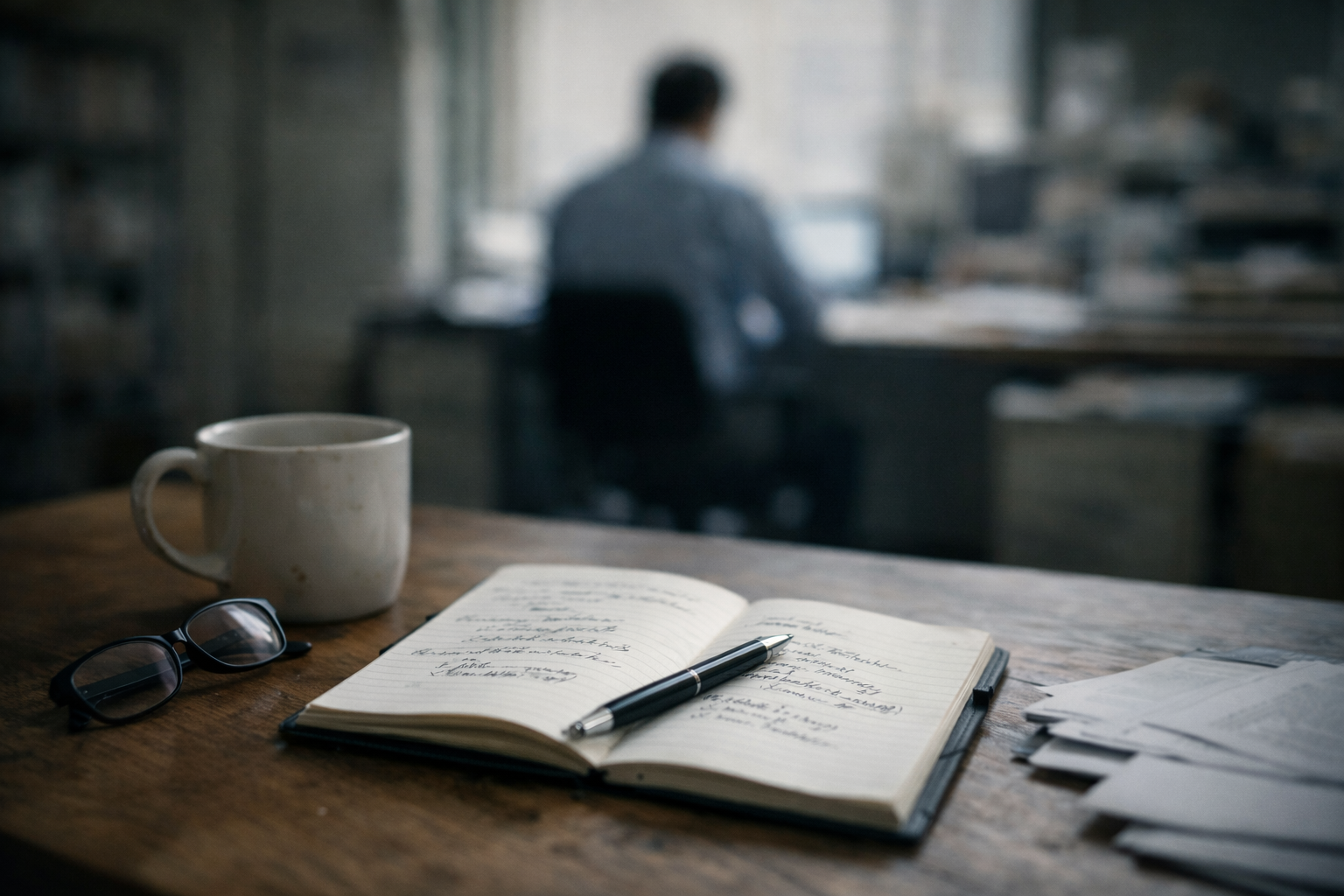災害はいつ発生するかわかりません。
2024年1月1日に発生した能登半島地震では、自治体職員や学校の先生ですら避難所の設営が困難な状況に陥りました。地域役員が帰省や旅行中だったり、本人や家族が被災している場合、すぐに駆けつけることができない──そんな現実を目の当たりにしました。
では、もし避難してきた一般の人々が自ら避難所を設営できたら?
混乱を最小限に抑え、よりスムーズな避難生活のスタートを切ることができるかもしれません。
先日は私は地域の防災訓練の企画・運営を行いました。
今回の避難所設営訓練では、地域役員や自治体職員に頼らず、「避難者自身が設営できること」を目指しました。
体育館に養生テープを張るだけで変わる避難所の秩序
今回の訓練では、体育館内のスペースを整理するために、養生テープを使って区画を分けることに重点を置きました。具体的には、
✅ 避難者ごとの生活スペースを確保する
✅ 壁沿いや中央に通路を設け、スムーズな移動を実現する
✅ トイレや出入り口への動線を整理し、混雑やトラブルを防ぐ
これらの工夫によって、避難所内の混乱を抑え、少しでも快適な環境を作ることが可能になります。
設営に特別な知識や道具は必要ありません。
体育館に避難してきた人々が、ただ養生テープを張るだけで、秩序ある空間が生まれるのです。
これは、災害時の「初動」において極めて重要なことです。
実施することで見えた課題と次のステップ
訓練を通じて、改めて「知っている」と「やったことがある」には大きな差があると感じました。
- 設営の方法を事前に知っているだけでは、実際には動けない
→ 実際に手を動かす経験が大切 - スペースを仕切ることで、自然と秩序が生まれる
→ 通路や区画があるだけで避難所の機能が大きく向上する - 共感してくれる仲間が増えれば、より実践的なマニュアルが作れる
→ 地域住民が主体となる設営の仕組みづくりへ
今回の訓練を通じて、多くの方々に避難所設営の大切さを知っていただきました。
今後は、備蓄倉庫の棚卸を実施し、実際の物資と運用の流れをさらに整理していく予定です。
避難所運営において「何があるのか、どこにあるのか」は極めて重要であり、これもまたデータ化・可視化によって課題を明確にし、より実践的な運用へとつなげていきます。
「実施」→「可視化」→「改善」──私たちの考え方
今回の訓練で実感したのは、「実施することで課題が見え、次の改善につながる」ということ。
これは、私たちが医薬品のサプライチェーンコンサルティングで日々取り組んでいる「データ化」「可視化」「数値化」と同じプロセスです。
✔ 実際にやってみることで、問題点が浮かび上がる
✔ データとして整理することで、解決策を考えられる
✔ 次のステップにつなげることで、より強固な仕組みができる
この考え方は、医薬品業界に限らず、あらゆる分野に応用できます。
私たちは、データをもとに現場の課題を見える化し、改善をサポートすることを得意としています。
「現場を可視化し、より良い仕組みを作りたい」
「データに基づいた業務改善を進めたい」
そうしたお考えをお持ちの方、行動に移してみたいという方は、弊社までご相談ください。