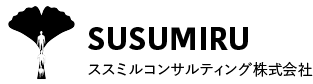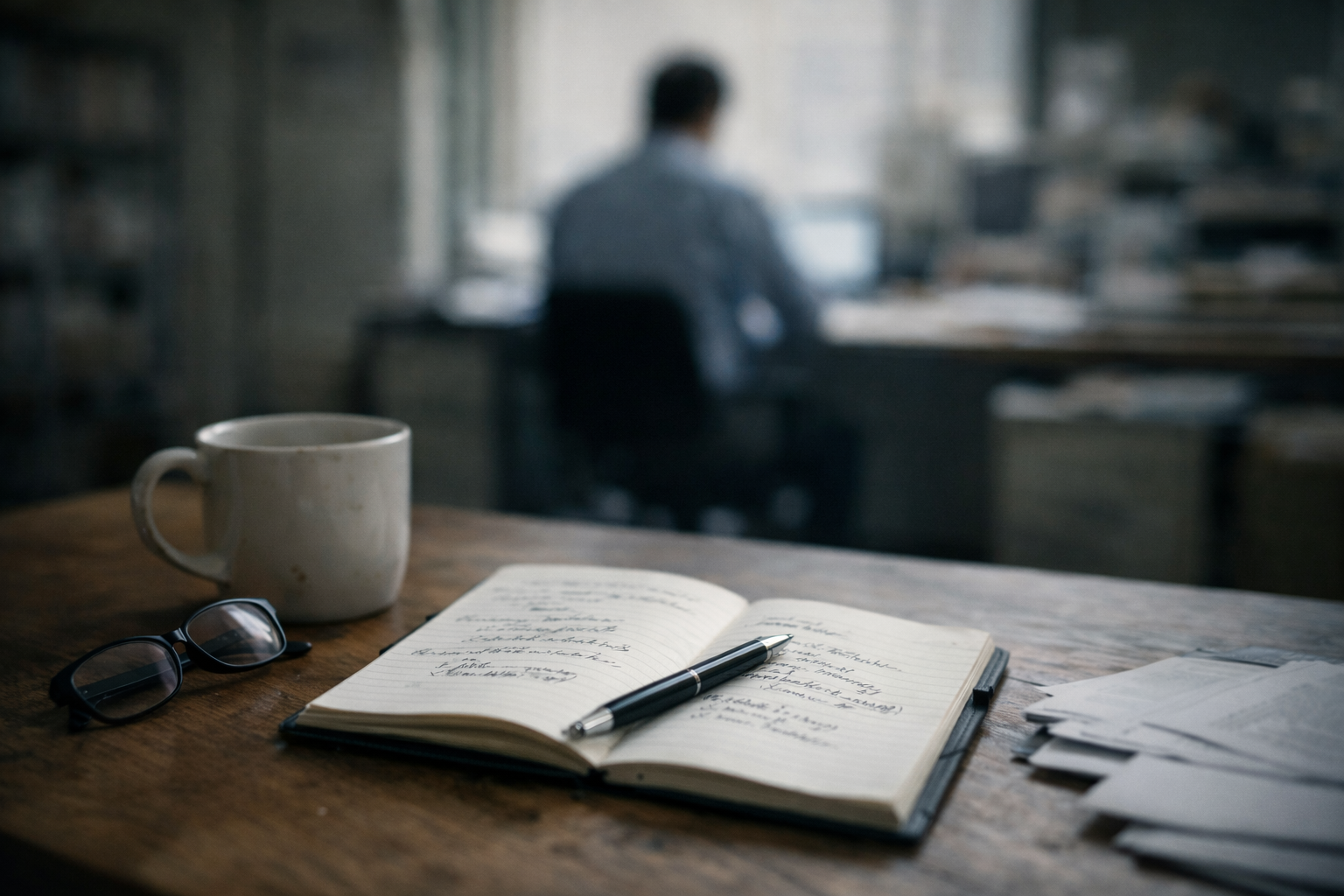先日、私が購読しているアート系のメルマガにこんな話がありました。
「紙と鉛筆を渡されて、『リンゴを描いてください』と言われたら、多くの人は実物を見ずに描き始める」
頭の中のイメージで、丸い形、上のヘタ、赤い色──なんとなく描けてしまう。
けれど、実物を目の前に置いて描こうとすると「全然違う」と気づくのです。
表面には凹凸があり、赤だけではなく黄色や白も混じっている。
光の当たり方でツヤの強弱が変わり、置かれた面は一点で支えられている…。
「知っているつもり」のリンゴと、「実際に観察したリンゴ」はまるで別物。
この体験を通じて、メルマガの筆者は「私たちは意外とちゃんと見ていない」と気づかせてくれました。
サプライチェーンも同じこの話を読んで、私はサプライチェーンも同じだと思いました。
私たちは「この原薬は中国から入ってくる」「この添加剤は国内メーカーが供給している」と頭の中でイメージします。
けれど実際に観察してみると、想像と違う現実が見えてきます。
- 実は一社依存になっていた
- サプライヤーの採算が合わず撤退寸前だった
- 技術者が高齢化し、後継がいない
- 物流が止まると代替ルートが存在しない
「見えているつもり」と「本当に見たときの姿」のギャップ。
それをどう埋めるかが、安定供給の核心にあるのです。
観察から始まる安定供給
リンゴを描くときのように、サプライチェーンも「観察」から始まります。
- データを可視化する
- リスクを洗い出す
- 現場に足を運んで実態を知る
そのプロセスを繰り返すことで初めて、持続可能な仕組みを築くことができます。
そして「ちゃんと見る」ことに時間と集中力を割いた分だけ、新しい気づきが生まれ、将来のリスクを防ぐ力になると私は思います。
結び
「見ているつもり」のサプライチェーンから一歩進み、「本当に見る」こと。
その先にこそ、医薬品を切らさない社会を支えるヒントがあるのだと思います。