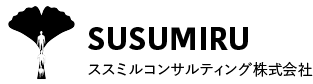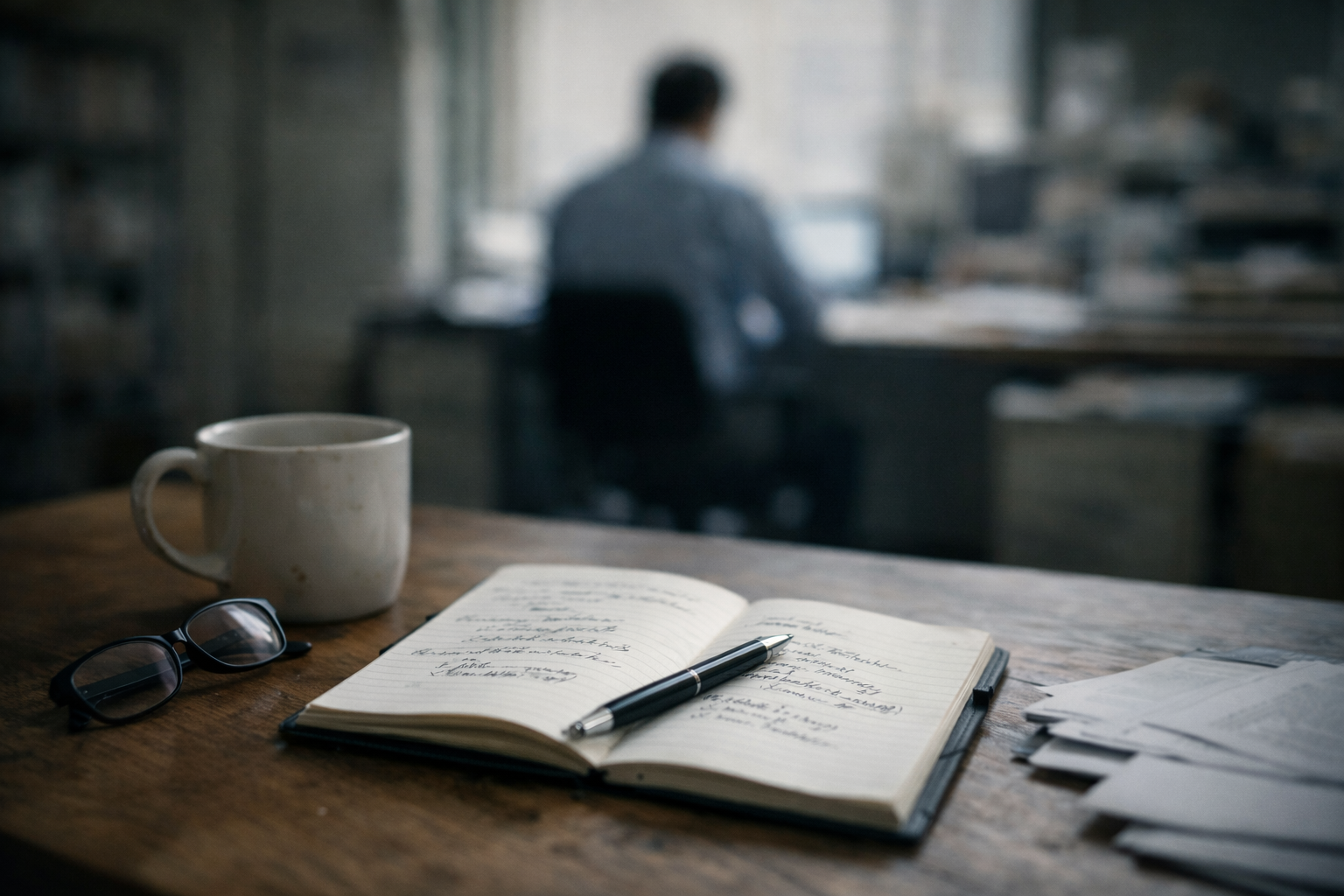7月30日、カムチャツカ半島沖で発生した大きな地震により、日本にも津波警報が発令されました。
後日、TV朝日の報道では、警報発令時の日本国内にいた外国人観光客の対応が取り上げられていました。慣れない土地で、どこに逃げればいいのかわからず、不安な時間を過ごした方もいたようです。
でも、これって私たち日本人にも起こりうることだと感じています。
ハザードマップ、見てるのは「自宅だけ」?
翌日、地域防災に関わる知人たちとLINEグループでこの件について話をしていました。
その中で話題になったのが、「災害リスクって、自宅周辺しか把握していない」ということ。
たとえば、出張や旅行で訪れた場所。
そこが津波や土砂災害、浸水などのリスクがある場所かどうか、皆さんは事前にチェックしていますか?
私は先月、宮城県の南三陸町や名古屋市の名古屋港といった、津波被害が想定される地域に出張していました。
現地では、「高い場所はどこか?」「山はどちらにあるか?」といった点を確認するようにしています。
地震は突然起こりますが、津波は到達までに少し時間があります。その“少し”の時間が、命を守る判断を可能にしてくれるからです。
知らない土地では、ハザードマップが「探しにくい」
とはいえ、現地での備えには不便な点もあります。
名古屋港の展示会を訪れたとき、スマートフォンで周辺のハザードマップを調べようとしましたが、正直、使いづらさを感じました。
知らない土地では「今、自分がどこにいるのか」が分かりにくく、地名や住所の入力に手間取ってしまいます。
そのときに見つけたのが、位置情報から現在地のハザードマップを表示してくれるWebサイト。
とても便利だったので、スマートフォンのホーム画面に追加して、すぐ見られるようにしました。
防災も、仕事も。「事前に知る」ことが未来を支える
ススミルコンサルティングでは、医薬品の原薬サプライチェーンを支える仕事をしています。
災害が発生したとき、必要な薬が届かない状況は命に関わります。
だからこそ、どこにどんなリスクがあるのかを「事前に知る」ことは、私たちの業務でも非常に重要です。
こうした思いから、私は現在「災害備蓄管理士」の資格取得に挑戦しています。
医薬品の安定供給という視点とあわせて、現場でも活かせる防災の知識を身につけたいと考えています。
出張や旅先でも、ほんの少し意識を向けるだけで、できる備えはあります。
そしてその備えが、私たちの暮らしや仕事を守ってくれると、信じています。